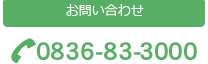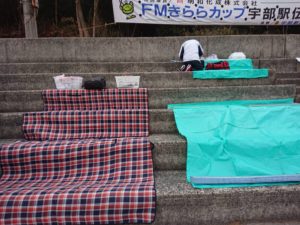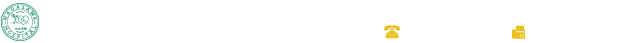新着情報 一覧
面会制限のお知らせ
新型コロナウイルス感染症対策として、面会は引き続き制限させていただいております。流行が収束するまで家族以外の面会を禁止いたしております。
また、ご家族でも体調不良(37.5度以上の熱や咳・鼻水、下痢)がある場合は禁止させていただきます。
入院患者様の安全のため、ご協力をお願いいたします。
入院患者様のために折り紙作品等を展示しております。
長沢病院のトップページはこちらです。
マラソン部活動報告「FMきららカップ 宇部駅伝」
令和2年2月2日(日)にFMきららカップ「第37回宇部駅伝競走大会」が開催されました。当院も1般2部に出場しました。1部は68チーム、2部は112チームがエントリー、大会は賑やかな様子でした。長沢病院マラソン部は112チーム中、なんと・・・100位でした。縁起の良い数字ですね!
曇り空でしたが、雨は降っていないので良かったです。
早起きして、マラソン部の場所確保も大丈夫です。
宇部新川ライオンズクラブさんからのぜんざいやお餅の無料配布がありました。
寒い中、身体が温まりました。とても美味しかったです。
1般2部の様子です。マラソン部が一名いますが、わかりますか?
2区の様子です。赤のタスキがいいですね!
3区の様子です。沿道にも応援される方が多いです。
4区の様子です。いい調子です。
みんなで和気あいあいとした様子でした。監督さんや補助員さんもありがとうございました。可愛い子供の応援も元気が出ました。みなさんお疲れさまでした。
長沢病院のトップページはこちらです。
作品紹介「節分」
今回の作品紹介は「節分」です。
節分は悪いものや邪気を落として、新しい年に幸運を呼び込む目的に行われてきました。
鬼さんと福さんが可愛く貼ってありますね。
年の数ほど豆を食べましょう。
美味しそうにできてますね。
皆さんいい笑顔です。
パクリっと、今年もこれで元気に過ごせます。
長沢病院のトップページはこちらです。
作品紹介「季節の飾り物」
1月もあっという間に終わりですね。
当院の作品も入れ替えになるので、そのまえに是非ご覧ください。
クリスマス会でのフセグンジャーは格好良かったですね。
皆さん、今年は絵馬を書きました?
今年もレノファ山口を応援しましょう!!
華やかで良い感じな雰囲気ですね。
長沢病院のトップページはこちらです。
マラソン部活動報告「城下町長府マラソン」
令和2年1月19日(日)に城下町長府マラソンが開催されました。コースは下関長府中学校のグランドから城下町長府の街中を走ります。当院から10km、5kmに参加しました。
早朝は雨も降って、悪天候でした。
マラソン部はそんな中でも元気です!
いよいよ、開会式が始まりました。
おーっと、ゆるキャラ達が沢山です!!
ジョージロー?勇ましいですね。
アップダウンの多いコースでした。
全員無事に完走しました。皆さんお疲れさまでした。そして、開催スタッフや沿道で応援してくれた人達に感謝申し上げます。
次回は令和2年2月2日(日)に開催される「FMきららカップ宇部駅伝競走大会」に参加します。
長沢病院のトップページはこちらです。
新年のご挨拶
新年明けましておめでとうございます。 皆さまには健やかに新年をお迎えのことと心からお慶び申し上げます。令和2年が皆さまにとりまして良い年になりますことをお祈りしつつ、新年のご挨拶とさせていただきます。
新年のご挨拶の動画ができましたので、ぜひご覧ください。
長沢病院のトップページはこちらです。
年末年始の診療のご案内
当院の年末年始の診療について
下記のとおりとさせていただきます。
ご迷惑をおかけ致しますがよろしくお願いします。
令和1年12月28日(土) 午前中のみ診療
令和1年12月29日(日) 休診
令和1年12月30日(月) 休診
令和1年12月31日(火) 休診
令和2年1月1日(水) 休診
令和2年1月2日(木) 休診
令和2年1月3日(金) 休診
令和2年1月4日(土) 午前中のみ診療
長沢病院のトップページはこちらです。