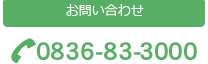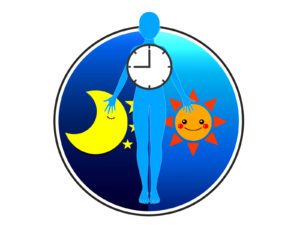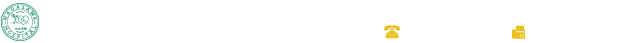栄養士のつぶやき「自律神経」
体調を崩しやすい季節の変わり目では、昼と夜の気温差が大きくなります。これらの時期によくみられる症状の一つとして、頭痛があります。
原因
寒暖差による体調不良
ストレスによる自立神経の乱れ
生活環境の変化による生活リズムの乱れ
睡眠不足による乱れ
自律神経に良い食べ物
・バナナ(トリプトファン、ビタミンB6、炭水化物)
・乳製品(牛乳、ヨーグルト、チーズなど)(トリプトファン)
・大豆製品(トリプトファン)
・さつまいも(ビタミンB6)
・いわし(トリプトファン・ビタミンB6)
・くるみ・えごま油・アマニ油(オメガ3脂肪酸(不飽和脂肪酸))
・白米(麦・玄米・雑穀を混ぜたもの)
自律神経に良い食べ物を摂取することで、セロトニンというホルモンが増え、良い睡眠をとることができます。セロトニンを体内で生成する栄養素は、必須アミノ酸の一つであるトリプトファン、ビタミンB6、炭水化物です。
トリプトファン…牛乳、ヨーグルト、チーズ
ビタミンB6…いわし、さつまいも
炭水化物…白米
中でも特に良いものはバナナです。上記の3つの栄養素を含んでいるのでおすすめです。
長沢病院のトップページはこちらです。